
若手リーダーが抱える悩みを、ベストチーム・オブ・ザ・イヤー 実行委員長の齋藤孝先生がズバッと解決! 全5回、1回1質問で具体的な解決策やそれに基づく理論なども交えます。第5回は「成功体験に関する考え方」について。
年上のチームメンバーに仕事の取り組み方を変えてもらうには?
年上のチームメンバーに仕事の取り組み方を変えてもらうには? 年齢が上で社会人経験が豊富な人がチームにいます。こだわりが強く、自分なりのやり方を崩そうとしません。過去の成功体験もあると思うのですが、ビジネス環境の変化が激しい最中、自分を変えることに抵抗を持たず、新しい環境に適応した仕事をしてもらうにはどうすればよいでしょうか?
どんなチームにもこういった人はいます。これが難しい問題なのは「過去の成功体験にとらわれる」という言葉が常套句になっていることです。「過去の」「とらわれる」という言葉には、ネガティブな評価が入ってしまっています。
「過去の成功体験にとらわれる」と思うこと自体が1つの偏見と言えます。経験不足の人に「経験がないから……」と言ってしまうのと同じく、「過去の成功にすがりつく」と思うのもまた偏見なのです。
年上の人の話を聞く年下の人は「あー、この人は古い考え方だ」と思うわけですが、それも一種のネガティブな先入観ですよね。「時代は変わっているから……」と思うこともあるかもしれませんが、どう考え、どう進んでいくのが正解かは誰にも分かりません。逆に「過去の成功体験」がずっと通用する場面も多いのです。
結果がすべて。「過去の成功体験」という言葉に縛られるな
私は「結果がすべて」だと思います。結果の出る、出ないはその時々の局面によって変わりますし、過去の成功体験をなぞって同じことをやったらうまくいった、という場合もあります。
「自分のブームは10年に1回ぐらい来ます」──。漫画家の本宮ひろ志先生がおっしゃっていた言葉です。『男一匹ガキ大将』『俺の空』『サラリーマン金太郎』でマンガブームが起こりました。登場する主人公の顔はだいたい同じ、性格も似ています。
本宮先生は「自分があんまり動いちゃだめだ」といった趣旨のこともおっしゃっていました。あえて自分から動かないことで、ブームや流れが自分に回ってくることもありえるわけです。
もしみなさんの周囲に、昔の成功体験を語っている方がいた場合、その人の発言内容について、本当に見込みがあるかをそのつど判断してみることをお勧めします。内容の良し悪しや是々非々はいったん置いておいて、発言内容だけを見てみるというのも良いと思います。
「仕事で先輩後輩関係ない」と言い切れない場合
「日本では、年上は扱いづらい」という認識があるのもまた事実です。欧米で仕事をされてきたカーデザイナーの奥山清行さんは、とあるインタビューで「日本に帰ってきた時は、急に仕事がしにくくなったと感じている」と話されたそうです。
ものの言い方に気を使わないといけない雰囲気があるからかもしれません。会社の会議でも全員が平等な一票を持っているわけではありませんし、上下関係が残っている社会では年上の人を尊重しなければならない。正直に言うと、ちょっと面倒な一面が残っていたりします。
仕事をする上で「先輩も後輩もない」と踏み切れるか。心情的に難しいものです。まずは敬語を上手に使って、チーム全体で気持ちよく仕事をしていただくことから始めてみるとよいです。
相手を敬い、過去の経験が生きる場面を作る
チームのメンバーが仕事のやり方を変えられない場合もあるでしょう。その場合はルーティーンな仕事を数多く担当してもらうのも1つの解です。
仕事は「新しいこと」ばかりではなく、型にはまった仕事も多く存在します。そこは過去の経験値が生きる分野です。人に応じてそういった仕事を多く配分すると、チーム内での仕事の住み分けも自然とできてくるでしょう。
「年上の人だから仕事ができない」と無理に決め付けてはいけません。人によって生きる仕事、できる仕事が必ずあるわけです。そこを確実にこなしてもらって、チームの仕事の負担のバランスを取るのがよいです。
仕事の依頼は、その人を尊重し、不信感を持たずに仕事を任せることが大事です。「私達はこの分野でこういったアウトプットが必要ですので、後方支援をお願いします」というように伝えるとよいです。
ほめる技術
できた仕事を評価することを忘れてはいけません。任せた仕事が完了すれば「ありがとうございました」とお礼をしたり、「助かりました、お陰で仕事がやりやすくなりました」とねぎらったりすることが大切です。
ほめる・ほめられるという動作を通じて良い人間関係が作られていきます。人はいくつになってもやりがいを求めるものですので、「どう役立ったのか」や「助かった」というていねいな気づかいの言葉が一言あるだけで、良い関係ができていくものです。
頑固に見える人ほどあまり褒められたり評価をされなかったりしています。逆に、良い人間関係やなごみを求めているとも言えます。だからこそ、ほめることは大切です。
「この人は頑固だ、自分を変えようとしない」という気持ちがもし生じた場合は、それは悪循環への第一歩です。無理にその人を変えようとせず、あきらめてその人にできることをやってもらうのも一考です。
指示と同時に相手を敬う
指示の仕方には注意が必要です。指示が明確でないと、見当はずれなアウトプットにつながる可能性があるからです。最初は「こういうふうにしてください」と具体的な指示を示すのがお勧めです。
成果物には「これで良いですね」といって受け取り、修正をして、伝えるといったことを繰り返していく必要があります。最初は時間が掛かりますが、仕事が型にはまり出すと、後はそれを実行するだけでよくなります。
人を変えるというのはとても難しいです。他者が人を変えるためには膨大なエネルギーを要します。私はあきらめが早いほうですので、「この人は変わらない」と感じた瞬間に、その人ができるシンプルな仕事をたくさん担当してもらおうと考えます。そしてたくさんほめます。
自分を変えるのだって難しいのに、他人を変えられる?
「柔軟性がない」という人はだいたいどの部署にもいます。だからこそ、その人に確実に任せられる仕事を見つけていくのがいいです。
人は変わらないものです。50歳になって大きく変わるというのは、まずありません。40歳でも変わるのは難しいものではないかと思います。
変わる可能性があるのは30代前半くらいかもしれません。逆にそれを過ぎて30代後半くらいになると、男女ともに急速に考え方が凝り固まってくると感じます。
職場には仕事が上手に見える人もたくさんいます。それらの人も40歳前後を境に、仕事の仕方は大方決まってくるのではないかと思います。
自分のスタイルで仕事をし、結果を出している人がいるとします。彼らはその時々の局面に応じた仕事のやり方で実績を挙げてきたのだと思いますが、仕事の仕方自体はずっと同じという人も少なくないはずです。
仕事の仕方が強引な人がいて、何かがあればネゴシエーションをして成功をしてきた。このやり方を20代、30代と突き詰めてきた場合、40歳以降もずっとそのやり方にこだわり続けてしまいがちです。結果を出しているなら、誰からも文句を言われないでしょう。
結果が出ていると、同じ仕事をしていても「すごい。この人は世間を知っている」という印象になるわけです。逆に結果が出ていない場合は「古いやり方をしている」と印象を周囲に与えてしまうかもしれません。
若い人の方が実は頭が固いって本当?
仕事のやり方を知らず知らずのうちに変えられなくなっている人は多いです。柔軟性は、たいていの人が持ちあわせていないものです。
よく「若い人の方が、柔軟性がある」と言われますが、本当にそうでしょうか? 実はそうでもないと感じる場面もあります。これまでの経験がない分、柔軟性に乏しくなる場合があるのです。
私は大学の教員として、学生とよく接しますが、若いからといって柔軟な人ばかりではないですよ。むしろ頑固な一面があって、「自分の考え方に固執していないか?」と感じることもあります(笑)。
柔軟性に乏しい人がチームにいた場合は、本当に重要なプロジェクトには加えないことも、時には大事です。その人の使い道を考えも疲れてしまいますので、「最後の書類の仕上げだけお願いしますので、それまでお休み下さい」と伝えて、残りのメンバーで全部仕事に着手してみるのもありです。
その人が重鎮だった場合は、ご意見を伺うようにして、実作業はほかのメンバーでやる。その人を尊重しつつ、時々仕事の報告をしておくと良いかもしれません。
「仕事が進まないストレス」が積み重なるほどしんどいことはない
「働くのが根源的に嫌だ」という人は実は少ないです、仕事が嫌だと言っている人の多くは、仕事自体ではなく、仕事が進まないことにいらだちを感じるわけです。
チーム運営で重要なのは「ストレスを少なくすること」です。その人がいてチームがうまく回らなければ、それはみんなのストレスになりますから。
もしチームメンバーがストレスにまみれているなら、仕事のできる人3,4人でワーキンググループを作り、密やかにパッパッと決めて進めていくと良いですね。
ワーキンググループに入っていない人にとって、この進め方は楽なわけですから、チームにとっては良いことです。チームメンバーは7人でも、実質は3、4人で仕事している。そんなケースがあってもいいと思いませんか。もちろん、全員が動けるのが理想です。
齋藤孝先生のお悩み相談室バックナンバー
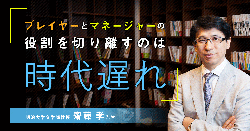 プレイヤーとマネージャーの役割を切り離すのは時代遅れ
プレイヤーとマネージャーの役割を切り離すのは時代遅れプレイヤーか、マネージャーか──。この役割は完全に分かれる時代でもないと思っています。その人がチーム内で任される役割によって、誰もがマネージャーにもプレイヤーにもなり得るわけです。...
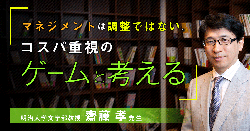 マネジメントは調整ではない。コスパ重視のゲームと考える
マネジメントは調整ではない。コスパ重視のゲームと考える達成に向けたプロセスを調整ではなく、一種のゲーム感覚で考えてみることをお勧めします。「誰々が調整しなければならない」ではなく「チームで勝ちにいく」という意識が芽生えてくるからです。「今回の仕事は色々なプロセスを省けて少ない労力で終えられた。うまくいった」となればしめたものです。 ...
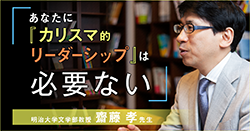 あなたに「カリスマ的なリーダーシップ」は必要ない
あなたに「カリスマ的なリーダーシップ」は必要ない今、カリスマ的なリーダーは求められていないと思います。まずは「何の目的のために、何をするのか」というビジョンがあり、優先順位をさっと決めて、段取りを組み、最終的な責任を持ってくれる、つまり後始末をつけてくれる人。この4つの素養を持つ人なら、だれでもリーダーの資質があるといえます。...
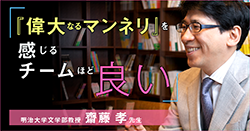 「偉大なるマンネリ」を感じるチームほど最高である
「偉大なるマンネリ」を感じるチームほど最高である「偉大なるマンネリ」になればなるほど、チームにとってはいいのです。「10年も一緒の人と会議をしている」「言わなくても分かることが多いから、いつでもリラックスできる」という、まるで我が家で過ごすようなマンネリの良さってあると思います。...
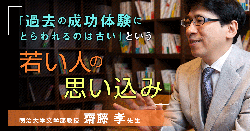 「過去の成功体験にとらわれるのは古い」という若い人の思い込み
「過去の成功体験にとらわれるのは古い」という若い人の思い込み年上の人の話を聞く年下の人は「あー、この人は古い考え方だ」と思うわけですが、それも一種のネガティブな先入観ですよね。「時代は変わっているから……」と思うこともあるかもしれませんが、どう考え、どう進んでいくのが正解かは誰にも分かりません。逆に「過去の成功体験」がずっと通用する場面も多いのです。...