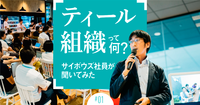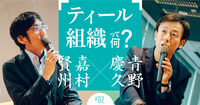サイボウズ式編集部です。11月7日に、サイボウズ式ブックス初の書籍『最軽量のマネジメント』
が発売されます。
「チームワークあふれる社会を創る」の理念のもと、自社では100人100通りの働き方を実現するサイボウズ。サイボウズの副社長として、管理部門の責任者として、一人のマネジャーとして、「100人100通り」の働き方を実現するまでやってきた山田理が考える、新しいマネジメント論をまとめた1冊です。
「これからのマネジャーはどうすべきか」という重荷ではなく、「どうすればマネジャーの仕事を減らせるのか」という軽やかさを示したい。本書は、寄せられた過度な期待と責任から、マネジャーを解放するための本です。
出版にあたり、最軽量のマネジメントの「はじめに」を公開します。マネジメントに悩みを抱えるすべての方の助けになれば幸いです。
はじめに「どうすれば、マネジャーの仕事を減らせるのか?」
![『最軽量のマネジメント』の書影]()
そもそも、マネジャーは本当に必要なのだろうか
「マネジャー」は当たり前のように、どの会社にもいます。
その総数が果たしてどれくらいなのかはわかりませんが、おそらく社長や役員の数よりも圧倒的に多いでしょう。
「係長」「課長」「チーフ」「リーダー」「事業責任者」......呼び方はいろいろありますが、企業の経営課題のひとつには、かならず「マネジャーの育成」が挙げられています。それだけ、会社にとって大切な役割を果たしているのでしょう。
ご多聞に漏れず、サイボウズでもマネジャーの人選や採用、育成については、これまで頭を悩ませてきました。
では、そもそもマネジャーはなぜ必要なのか──あるいは、必要だったのか。果た して、これからも本当に必要なのか。ここから話していきます。
「多様性」の陰で生まれたのは、「世代間のギャップ」
「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と評された 年代バブル時代。
巷にはモノが溢れ、株や土地の価格が上がり、給与も増え、ブランド品も身近になり、若者は夜をディスコで踊り明かしました。
これがつまり、現在多くの大企業で、代表や役員を務める経営者層が生まれ育ち、暮らしてきた時代のことです。
その狂乱もつかの間、バブルが弾けます。
景気が底を打つ中で、人はだんだんと「生きるために何をするか」ではなく「幸せになるためにどう生きるか」を考えるようになりました。お金をたくさん稼ぐこと、 モノをたくさん持つことが幸せ、という昭和の幻想が崩れ、ライフスタイルを重視し て仕事とのバランスを考えたい、という理想が生まれました。
そして現代。インターネットとスマホの普及により、その理想は現実になりました。
場所に依存しないコミュニケーションが容易になり、「働く場所や時間を自由に決 めたい」という価値観が生まれ、一人ひとりの理想は多様化していきました。
その一方、インターネットとスマホを活用する世代と「それ以前の世代」のコミュニケーションコスト......ひいては価値観のギャップが、見過ごせない現実として生じてきたのです。
2015年に行われた、興味深い国際調査の結果があります。
ISSP(国際社会調査プログラム)によると、「自分の職場では、職場の同僚の関係は良い」と思っている人の割合において、日本は調査対象37カ国中、最下位でした。 日本人と気質がよく似ていると言われるドイツが、 2位の93.4%という数字に対 し、日本は69.9%。
しかも、2005年調査時の数字は81.5%。 10年前と比べても大幅に悪化しています。つまり、この数字が示すのは、日本の組織のあり方が多様性の時代に追いつかなくなっている、という現実です。
では、その原因はどこにあるのでしょうか。
![ISSP(国際社会調査プログラム)による、「自分の職場では、職場の同僚の関係 は良い」と思っている人の割合のランキング調査]()
トーナメントシートみたいな組織図は「情報を集約する仕組み」だった
これまでの会社の常識というのは、明治、大正、昭和、つまり「インターネット以前」の時代につくられたものです。
それまでの時代と今の時代でもっとも違うのは、情報の価値でした。
「情報」を集めるためには、基本的に人と会う必要がありました。そして、共有するにも対面で集まらないといけなかった。
つまり、情報を集めるにも伝えるにも、場所と時間のコストがかかったのです。
そのため、ひとつのチームは、できるだけ同じ時間、同じ場所にいることが前提でした。新入社員の頃、みなさんも何度も教えられたことでしょう。大切なのは「ホウレンソウ(報告・連絡・相談)」だ、と。
社員の情報が係長に、そして係長の情報が課長に、課長の情報が部長に伝えられ、部長が取締役に、取締役が社長に...... と、伝言ゲームのように伝わっていく。 さまざまな部署から拾い上げられた情報は、社長ないし経営陣のもとに集約さ れ、その情報をどこまで共有するかは、 上層部で判断する──。
よく見るあのトーナメントシートみたいな組織図は、実は「情報を集約するための効率的な仕組み」だったのです。
だからこそ、トーナメントシートの中間地点には「ハブ」としてマネジャーが配置され、情報が吸い上げられていきました。
![社長と社員の上下関係を役職ごとに階層化した図]()
マネジャーのもっとも大切な役割は、チームを管理することでした。管理する、とはつまり、ホウレンソウによって部下から吸い上げた情報、あるいは上からの情報に基づき、「意思決定」をしていくことです。
その際、当然マネジャーは部下が知らない情報を持っています。その上これまで培ってきた経験や知識もあるはず。だからこそ、部下にはできない意思決定ができた、というわけです。
偉い人って一度で全部を伝えてくれない アレはなぜだったのか
経験がありませんか? 課長や部長に、情報を「小出し」にされたこと。偉い人って、一度に全部を伝えてくれないですよね。「どうしてですか?」と聞いても、煙に巻かれたりすることもあります。
「あれってどういうことだったんだろう?」と、よくよく考えてみると、すべて情報を明かしてしまうと、「上司と部下が同じレベルになってしまう」からだったのです。 つまり、情報格差を意図的に生み出すことがとても重要だったのでしょう。
アホらしい、と思うかもしれません。 しかし、時代背景を思い出せば「もっともなことだったんだな」とも感じるのです。
わたしも昭和生まれの昭和育ちです。インターネットがない時代に社会人になりました。携帯電話はもちろんなく、外出先からの連絡手段は公衆電話のみです。電話機の上には10円玉が山積み。そこからテレホンカードになっただけで「便利になったもんやなぁ」と思っていました。
彼女と電話で話すには、自宅にかけ、お父さんの「だれや、お前」という大きな壁を突破しないと、話すことさえできません。就職してから引っ越した独身寮には、食堂に1台しか電話がありませんでした。新人が順に電話番をやらされ、かかってきた電話をとり、館内放送でいちいち先輩を呼び出していました。
そんな時代、あるいはもっと前につくられた常識の中で生まれた組織が「会社」なのです。
情報を得るためにかなりのコストを要していた環境だからこそ、それを持っている人に権限があった。裏を返せば、情報格差こそが権威やお金を生み出す手段だった。そんな時代だったのです。
インターネットは「組織の階層」を破壊した
しかし、インターネット以降の世界で、情報は根本的に安くなりました。それはもう、バブル期の株価の下落なんて比べものにならない暴落です。ITの力で、情報格差はほぼフラットになりました。
あらゆる情報が、あっという間に世界中を飛び回ります。だれでも簡単に発信できるし、共有できます。上司も部下も、 1秒で同じ情報にアクセスできてしまいます。
サイボウズが提供するグループウェアも、そんな世界を実現するために生まれたものです。
そうなると、「おれだけがこの情報を持っているんだぞ」という権威は機能しなくなってきます。必死に隠しているつもりでも「ダダ漏れ」です。
こんな状況で、意思決定やチーム管理を、これまで通り──つまり「自分しか知らないから、おれが偉い」「そのおれが決めたんだから、つべこべ言わずにやれ」というやり方で続けるのは、とても大変なことです。
みんなもう、知ってしまっています。年齢がほんの何歳か違うだけで、意思決定の能力はそう簡単に上がらないこと。同じ情報さえ与えられれば、若いメンバーでも同じ質の意思決定ができることを。
そしてさらに、自分の得意分野であれば、若いメンバーのほうがいいアイデアを出すことが普通に起こり得る、ということに。
働き方改革でいちばん損しているのはマネジャーです
働き方の多様化と、こうした世代間のギャップが生じている中で、いちばん損しているのはだれか?
間にいる、マネジャーです。
マネジャーには「上」から無茶ぶりが降ってきます。「うちの会社は働き方を改革 します」「フレキシブルに働かせます」「残業を削減します」「社員の満足度を上げます」── 。
いったい、どうやって?
だからといって、マネジャーには、会社のルールをつくったり変えたりする権限はありません。これがいちばん苦しいんですよね。
昭和世代の「上」は、実はだれもそのやり方を知りません。唯一の指示は「問題が起こらないようにうまくやって」とだけ。 なのに、会社の業績目標は変わらない。メンバーの成果目標も下げてはいけない。業務効率を良くし、社員のモチベーションを高く維持しなければならない。自分が持っている数字もある── 。
「できるかいっ!」
そんなことができるくらいなら、とっくにやっていますよね。
しかも、そのジレンマに対して「下」から突き上げられるのもマネジャーです。 「下」からは、「無理です」「どうすればいいんですか」「そもそも何のための働き方改革なんですか」と問われます。上司に相談にいっても、「それをうまくやるのが君の仕事だろ」とまた無茶ぶりされます。
部下のモチベーション維持の前に、自分のモチベーション......それ以前に、まともな精神状態を維持するのさえ難しいのではないか、と思うのです。
これまでの組織のあり方は、現在の大企業が、創業当初のベンチャー的な経営を脱して成長していく中で、その成功体験を元にできたものです。ですから、それを踏襲し、一生懸命頑張ることが美徳とされてきました。
終身雇用と引き換えに、会社への忠誠心が求められる。「24時間働けますか」と問われ、子どもが生まれようともマイホームを買おうとも、辞令ひとつでどんな場所へも飛んでいく。弱音を吐くやつは「情けない」と叱責され、ついて来られないやつは窓際に追いやられ、あまり意味のない仕事を渡される── 。
そんな時代の中で這いつくばって仕事を学んだ世代と、インターネット以降の時代に生まれ育った世代。その狭間で、これまでだれも経験したことのないほど困難なマネジメントスキルが求められている。それが今の時代のマネジャーなのです。
「上」からの指示の意図を汲み取り、「下」に対しては納得させ、コーチングし、ティーチングし、メンタリングする。そのために必要なスキルは、ビジネス書を読込んで学習する。自主的にセミナーにも足を運ぶ。もちろん、個人の成果も出しながら、です。
「そんなパーフェクトヒューマン、どこにおんねん!」
あまりに酷です。この状況でうまくいく人がいるなら、それは奇跡か「もうけもん」です。
しかし、こんな状況の中でさえも、「やるからにはいいリーダーになりたい」という強い責任感を持ちながら、押し付けられた役割と戦っているのがみなさんなのだと思います。
みなさんが日頃、どんな責任や役割を負っているか、ちょっと棚卸してみましょう。会社の規模や仕組みによってバラツキはありますが、一般的にマネジャーの仕事は、大きく分けてこのふたつです。
ひとつは、プロジェクトマネジメント。そしてもうひとつは人材マネジメントです。そして多くのマネジャーが、基本的にはその両方を一手に担っています。
プロジェクトマネジメントには、目標を決める、意思決定する、進捗管理する、予算管理する、といった役割があります。人材マネジメントには、人材育成や採用、メンバーのモチベーション管理、評価などがあります。
さらに言うと、中間管理職としての報告や調整業務。実際はプレイングマネジャーである人も多いでしょう。これらの役割をすべて全うし、そのすべてに責任を取れる人がもしいるといたら、その人はすぐに今の会社を辞めて独立したほうがいいでしょう。きっと今より稼げるはずです。
「正直、全部は目が行き届いていない」「全然うまくいかない......どれもバランスよく、なんか無理じゃない?」そう感じる方は、素直な反応です。
そもそも、何でもかんでも役割をマネジャーに集中させてしまっていることが問題なのです。これらの仕事は、たった一人のマネジャーが抱え込まなければならないものなのでしょうか。
マネジャーを、もっとだれでもできる役割にしたい。抱え込みすぎているマネジメントの仕事と責任を分散させたい──。いや、むしろ「なくして」しまいたい。
サイボウズは、「マネジャー」という役割を、より希少価値が高い重要なもの、で はなく、もっと「大衆化」することに挑んできました。
サイボウズは人が人を管理することをあきらめた
サイボウズはグループウェアを提供する会社です。
グループウェアというのは、組織の中でやりとりされる情報、たとえば、スケジュール・顧客情報・メール・さらには企画書やファイルまで、あらゆる情報をオンラインで手軽に共有するためのツールです。
つまり、より良いチームワークを生み出すサポートをするもの。ですから、企業理念にも「チームワークあふれる社会を創る」と掲げています。
そして、わたしたちが考える理想のチームワークとは、「企業理念に共感して集まったメンバーが、お互いの個性を尊重し合い、公明正大に議論して意思決定し、自立したそれぞれが互いに作用し、助け合いながら、最大限能力を発揮できること」です。
お互いの個性を尊重し合う、ということは、それぞれの働きやすさを尊重する、ということ。それならまずは、サイボウズ自体がやるべきだ、と。
その結果、「100人100通りの働き方」を合言葉に、サイボウズではさまざまな働き方を実現してきました。
・育休は最長6年
・育自分休暇制度... 35歳以下は、退職後6年間出戻りOK
・複(副)業自由...会社資産と関係ないものは承認や報告の義務もない
・複業採用...サイボウズ側の仕事を複(副)業とする人向けの採用方式
・働き方宣言制度...いつ、どこで、どれくらい働くのか、は個人の自由記述式
サイボウズでは副業を「複業」と表現しています。従来の副業は、副収入を得るための「サブ」的な意味合いが強いものでしたが、サイボウズが考える「複業」は自分らしい個性的なキャリアを積むための「パラレル」、つまり並列なものです。
また、サイボウズの働き方は、もはや選択制ですらありません。「いつ、どこで、どれくらい働くのか、自分の希望する働き方を自由記述で宣言」します。
在宅で朝7時から働く人もいれば、基本は地方在住で週に2日リモート勤務する人、 9時出社するけれど途中複業で抜けて夕方に戻ってくる人もいます。まさに「100人100通りの働き方」です。 こうなると、もはや管理のしようなんて、ありませんよね。
「100人100通りの働き方」を目指した時点で、サイボウズは社員を管理することはあきらめたのです。そして当然、ここからサイボウズにおいてマネジャーに期待される役割は変わっていきました。
マネジャーは完璧じゃなくていい 「理想のマネジャー像」なんていらない
では、メンバーの幸せを第一に考える組織のマネジャーは、どうあるべきなのか──。
すみません。自分から言い出しておいてなんですが、もう、そういうのはやめにしませんか。「こういったマネジメントをすべきだ」「こんなマネジャーが理想だ」「こういう経験がある人が向いている」......。
見たこともない「理想の姿」を求めて、チェックリストをつくって、フレームワー クに落とし込んで、「再現性のある」ノウハウを見つけて......。
そんなやり方は、もう通用しません。だって、100人100通り、一人ひとり違う個性や価値観を持ったメンバーが、チームとして集まっているのですから。
みんな「管理される」のはイヤなはずなのに、マネジャーになった途端、「管理しよう」とします。なぜでしょうか。 十数年前のわたしもそうでした。そして、たくさんの過ちを犯しました。 ここで、はっきりさせておきたいことがあります。「マネジャーがメンバーのことをすべて把握し、管理する」なんて、無理です。
ただでさえ、「働き方改革で部下を早く帰さないといけなくなって、中間管理職が仕事を巻き取らないといけない」「部下の働き方が多様化したせいで、管理業務がかえって大変になった」......そんな声も聞こえる中で。
もっと、力を抜いて、「あきらめる」ことから始めてみませんか。
マネジャーが、なんでもかんでもできる必要はないのです。完璧じゃなくていい。完璧を求めると、自分も苦しくなるし、周りも苦しくなります。
あきらめる、という言葉を辞書で調べると、こう書かれてあります。「つまびらかにする。いろいろ観察をまとめて、真相をはっきりさせる」。
つまり、無理がある、と感じることにはどこかにかならず問題がある、ということ。それを明らかにせずに根性論だけでがんばる、というのはおかしいのです。
じゃあ、どうすればいいのか。
無理だと思うことには問題がある ➡︎ じゃあ一度それを明らかにしよう ➡︎ 明らかにすればマネジャーの仕事は絶対に減らせるはず
この視点こそが、この本で伝えたい「最軽量のマネジメント」なのです。
「はじめに」の最後に、この本の構成を紹介します。第一章では、まず「サイボウズが捨てた捨てたマネジメントに関する6つの理想」と題して、サイボウズが「100人100通りの働き方」を実現するまでに捨ててきた、古びた理想を書き出しました。まずはこの章を読んでいただき、これまでみなさんが背負ってきた重荷をそっと床に置いてもらいたい。
次に、第二章では「離職率28%から4%までの道のり」として、サイボウズがうまくいかなかったときのことをまとめました。 サイボウズでやってきた経験はありますが、すべてがすべてうまくいっているとは思わないですし、「これが正しい」とは言い切れません。わたしとみなさんは違う人間だし、サイボウズとみなさんの会社は違う企業だからです。
しかし、こうやったらうまくいかなかったという事実は、はっきりとみなさんに示すことができます。当てはまるかわからない成功例ではなく、過去の失敗例を参考に、みなさんのこれからを想像していただければと思います。
そして、第三章・第四章・第五章では、
・「みんなの考えていることが見えなくなったときこそ『ザツダン』」
・「最軽量のマネジメントは『情報の徹底公開』たったひとつ」
・「だいたいの問題は『説明責任』と『質問責任』で解決する」
として、どうすればマネジャーの仕事を減らせるのか、チームの多様な働き方を成り立たせることができるのか、何よりそのどちらとも両立するには、その実践例を共有します。
最後に、「会社そのものがなくなる時代に人はどうやって働くのか」として、わた しがシリコンバレーで見ている、すこし先の会社のあり方をお伝えしています。売上や利益、成果を第一に考える組織におけるマネジャーの教科書は、世の中に溢れています。
けれども、メンバーの多様性、働きやすさ......つまり、チームの幸せを第一に考える組織のマネジメント。その「実験結果」は、まだまだ足りません。働き方改革以後、理不尽な板挟みに合い、途方に暮れるマネジャーにとって指針となるような......迷ったとき、ふと夜空を見上げると目に映る北極星のような、そんな「レポート」にこの本がなればと思います。
『最軽量のマネジメント』目次
![はじめにと1章の目次]()
![2章と3章の目次]()
![4章と5章の目次]()
![6章とおわりにの目次]() 最軽量のマネジメント(サイボウズ式ブックス)
最軽量のマネジメント(サイボウズ式ブックス)
『最軽量のマネジメント』の予約・購入は
こちらから。ご意見・ご感想は、Twitterのハッシュタグ「
#最軽量のマネジメント」までお寄せください。