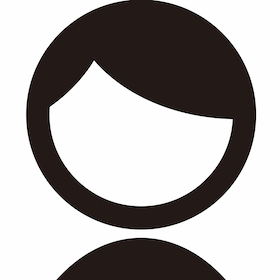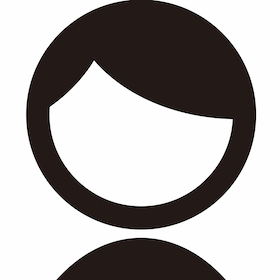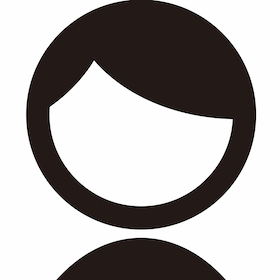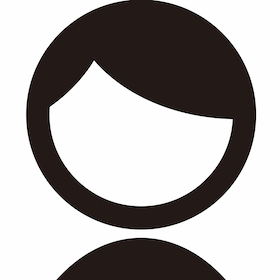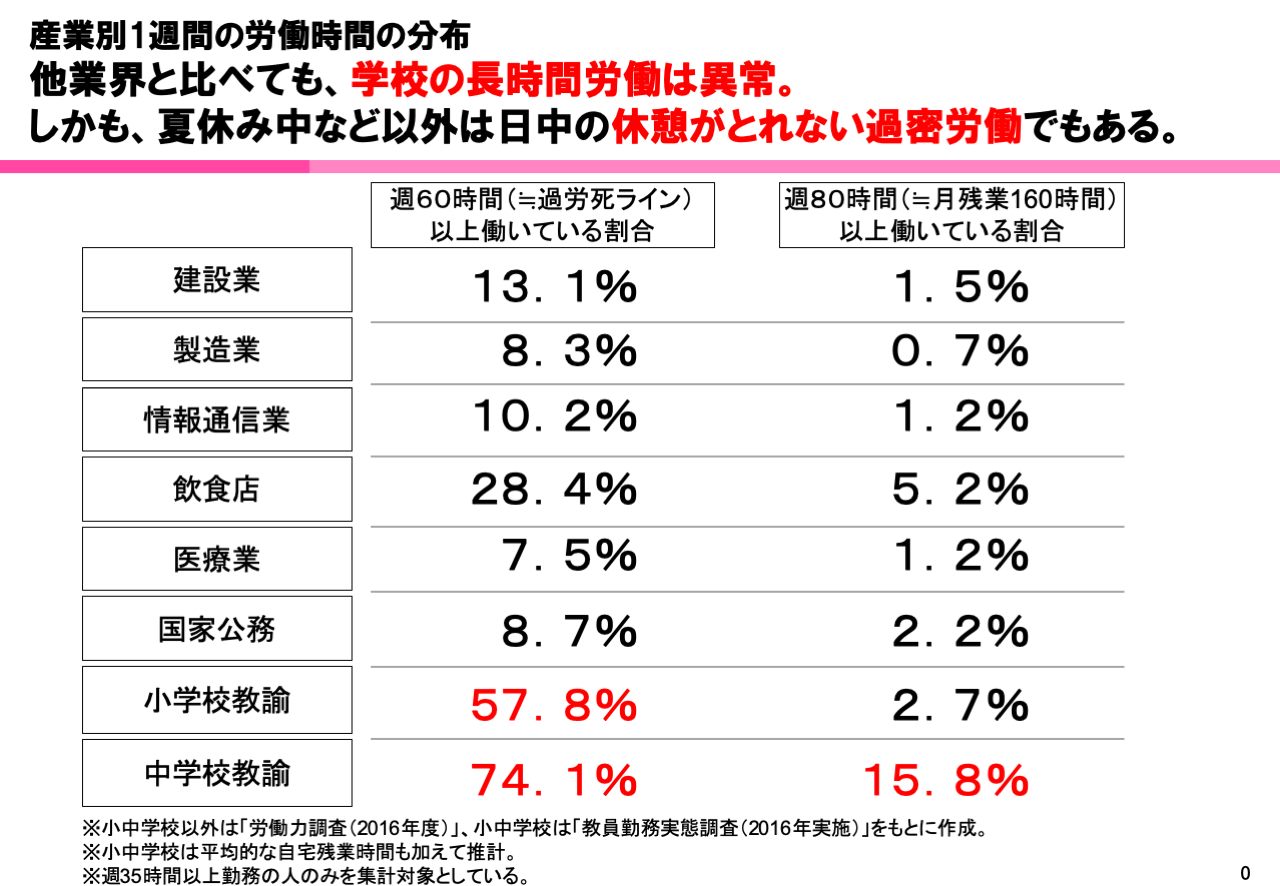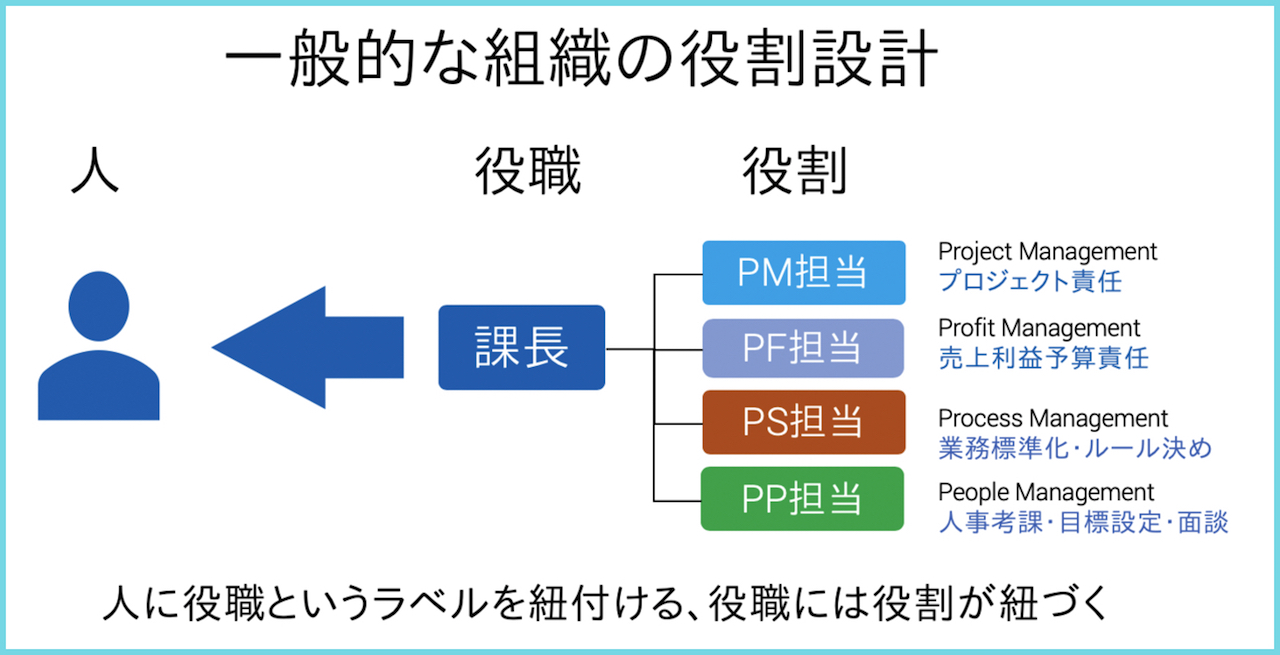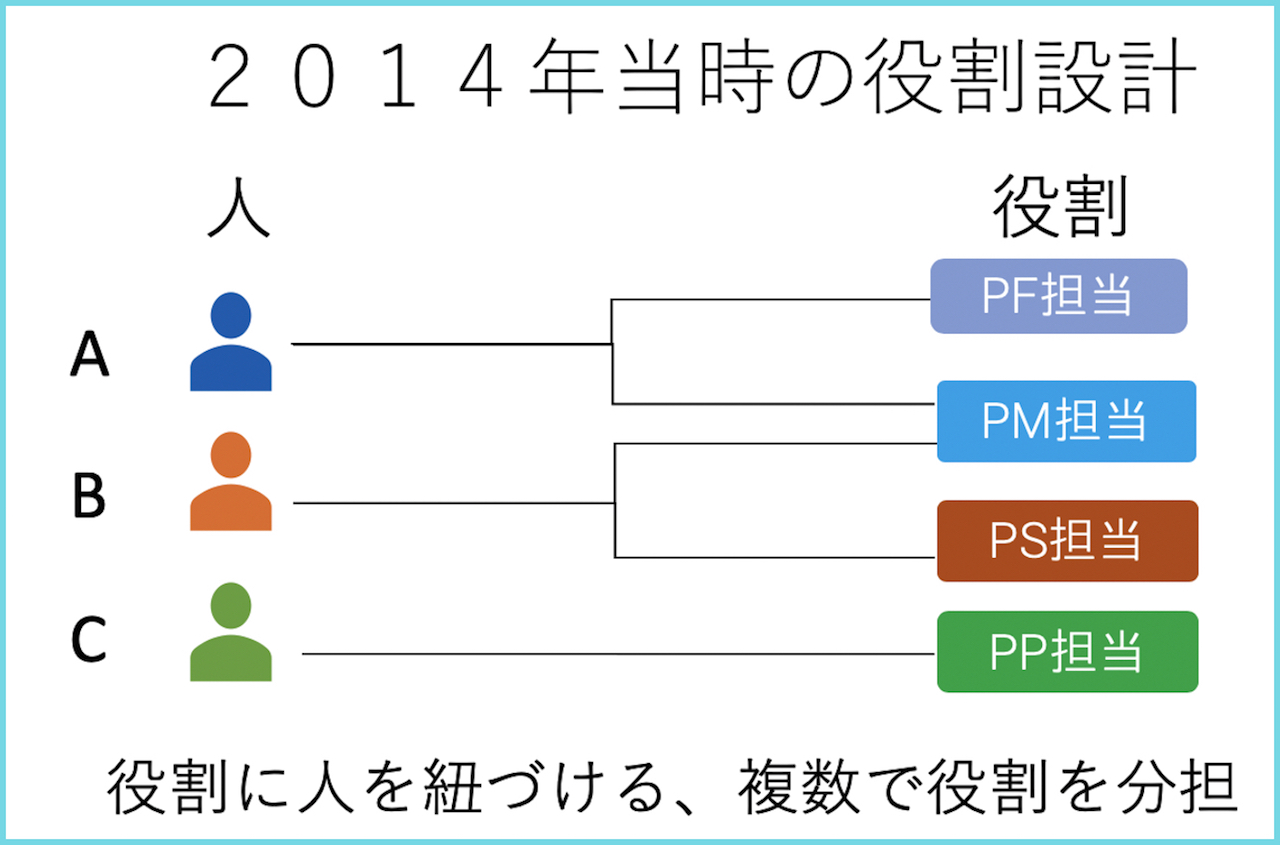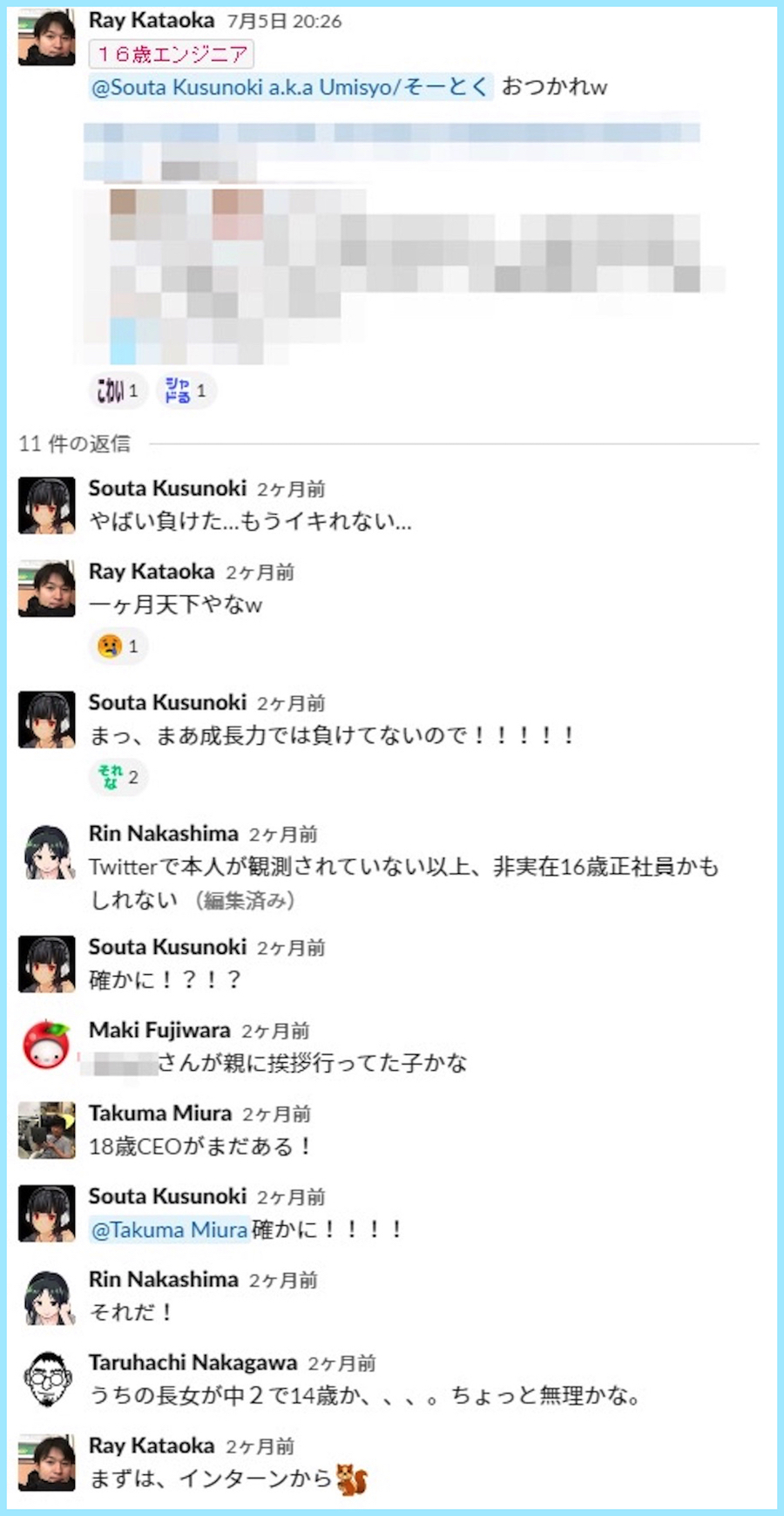人口減少や東京一極集中により、いま、地方は衰退の一途をたどっている。
総務省が2019年7月10日に発表した、住民基本台帳に基づく人口、人口動態および世帯数の調査によれば、日本の人口が1年間で43万人減少したそうだ。
日本でもっとも人口が少ない鳥取県の人口が56万人であることを考えると、ひとつの県がなくなる勢いで人口が減少していることがわかる。
ちなみに、人口が増えた都道府県は多い順に、東京(7.3万人)、神奈川(0.4万人)、沖縄(0.2万人)、千葉(0.2万人)、埼玉(0.1万人)で、それ以外の都道府県はすべて減少した。
わたしは地方の中山間地、新潟県妙高市に住んでいる。若い世代は都市部に出ていき、残っているのは高齢者世帯が多い。近年は、地域の集まりがあると「将来、この地域はどうなるのだろう?」と人口減少が話題に上がることも少なくない。
また、地方企業にとっても深刻な問題である。時々、地元企業の経営者と話す機会があるが、「人手が足りない」や「後継者がいない」などの叫び声が聞こえる。
これらの現状に、地方生活者として単純に思うのだ。「将来、この地域はどうなってしまうのだろう?」「このままでいいのかな?」と。
2年前に思いついた「地方×複業」のアイデア
わたしは、2017年5月からサイボウズで複業をはじめた。現在は地元新潟を軸に週2日、リモートワークで働いている。方向性としては「地方→東京」、生活は地方中心である。
地方を軸にするこの働き方は、やりたい仕事をしつつ、区や神社、公民館、消防団などの地域の活動にも参加できるのがいいなと思っている。「地方が軸で、都市部の仕事をする」人が増えると、東京一極集中を解消しつつ、地域も維持できるのかな? と思う。
![休日は地域の行事に参加する]()
休日は地域の行事に参加する
それに加えて、複業をはじめて比較的早い段階で気づいたことがある。それは、もし、この「逆の働き方」――つまり、「都市部のビジネスパーソンが、地方の企業で複業」できたら、人口減少や人材不足など地方が抱える課題を解決する一助になるのではないかということだった。
複業をはじめた当初に書いた、複業で「地方が軸、東京は拠点」に挑戦──人生100年時代を生きるために、サイボウズで地方中心の働き方を選んだでは、次のように触れた。
もし、今の会社でも働きつつ、地元の会社でも働くことができたら、緩やかに、安心して地方に移住できると思います。また、地方の会社が複業を始めたら、首都圏で経験を積んだ、移住を望んでいる人材と出会うきっかけになるかもしれません。
都市部には、「地元や地域の役に立ちたい」と思っている人がたくさんいる。一方、地方の企業は人材不足に悩んでいる。両者をマッチングできたら、おたがいの困りごとを解決できるのではないか、と。
1年前、「地方×複業」は否定的な意見が多かった
これを、なんらかの形にしてみたいと、1年ほど前、地方移住はハードルが高い。都心で働く人には「地方複業」がベストではないかという記事を書いた。
この記事の内容を一言で言えば、「いままで、地方創生と言えば移住推進だったけれども、移住はかなりハードルが高い。それならば、“地方で複業”からはじめてはどうか?」という提案だ。
つまり、仕事を通じて「都市部のビジネスパーソンと地方の企業をつなぐ」のである。これならば、いきなり移住しなくてもいいし、「普段はリモートワークで、月に1回出勤」のようにすれば、定期的な人の流れができる。
「地方で複業」記事への反応はさまざまだった。肯定的な意見はたくさんいただいた一方で、「片足だけ突っ込んだ地方での複業はあまり望まれていない」「住民票を移してもらわないと住民税も地方交付税も入ってこないので、あまり意義はありません」など、否定的な意見も多かった。
ごもっともな意見だと思う。
だが、否定的な意見をいただいても、わたしは「地方×複業」の可能性をあきらめることができなかった。そこで、自分でできる範囲から動くことにした。
まず、はじめたのは「周囲に話す」ことだった。
興味はある。だが、仕組みがない
機会をみつけては、地元企業の経営者や、地方にあるNPOの中間支援組織などで、「いままでにない人材活用の方法があるんです」と、地方×複業のことについて話した。
経営者からは、「アイデアはいいと思うけど、東京で働きながら、地方で複業できる人なんて実際にいるの?」という意見が寄せられた。だが、同時に「もし、そういう人が実際にいるなら、興味はある」という声も多かった。
しかし、次のステップでつまずいた。「そういう人がいれば、紹介してほしい」と言われたときに、紹介できなかったのだ。わたしはしょせん、田舎に住む一個人である。それほど多くの「地方の企業」や「地方で働きたい人」を知っているわけではない。
そう、地方の企業と都市部の人材をマッチングする仕組みがなかったのだ。
というより、そもそも、地方では「複業」という働き方自体が認知されていない。「地方×複業」を広める活動は、早々、暗礁に乗り上げたのである。
「地方×複業」を叶える方法を模索する
「この状況を、打開する方法はないか」……できることを模索した。
地方の企業と都市部の人材をマッチングするためには、両者をつなぐ「仕組み」と「地方自治体の協力」が不可欠なのではないかと考えた。
というのも、これを個人がやろうと思うとリソースが圧倒的に足りないし、地方創生は地域全体の課題でもある。ある企業が、利益のためだけに仕組みをつくるよりも、「地域みんなで」取り組む形にしたいと思った。
そこで、「地方×複業」や「二拠点生活」の課題や理想を話し合うサイボウズ式Meetupを企画した。
また、「地方×複業」の提案記事をきっかけに、イベント登壇の機会をいただいたりもした。
![イベント「これからの地域と仕事の未来を語ろう」]()
2018年11月13日に新潟県上越市で行われたイベント「これからの地域と仕事の未来を語ろう」の模様。地方のリアルと、これからの仕事の可能性について話し合った。平日の日中、地方開催の有料のイベントにも関わらず、150名ほどの人々が集まった
イベントに参加していただいた方々の想いや意見に触れて、「地方×複業」は、「地域にとっても、都市部のビジネスパーソンにとっても、おたがいにとってメリットがある取り組みに違いない」と思った。
「地方×複業」を実現する上でもっとも大切なこと
これまで、「地方×複業」について、関心があるみなさんと議論してきた中で、「大切なのは、間違いなくこれだな」と思うことがある。
それは、地方の企業と、都市部の人材と、地方自治体の「想いをマッチングすること」だ。
「副業」と言えば一般的に、本業以外で「稼ぐ」ことイメージする。そして、労働時間や報酬など「条件に見合った仕事」を探そうとする。ここにあるのは、「条件のマッチング」である。
だが、「稼ぐ」ことが目的なら、わざわざ地方でしなくても、都市部のほうが仕事はあるし、金銭的な効率もいい。
また、都市部のWebエンジニアが、地方企業のホームページを制作することは、別段、特別な話ではないように、都市部の人が「利益のためだけ」に地方の仕事をするのなら、わざわざ「地方×複業」なんて銘を打たなくてもいいはずだ。
だが、「地方×複業」はちょっと違う。これまで、イベント等を通じて、多くの「地方で複業してみたい」という人たちの声を聞いてきた。そこにあったのは、「稼ぐこと」が第一の目的ではなく、「地元や地域の役に立ちたいという想い」だった。
地方×複業では、この「想い」がもっとも大切なのだ。
これは、地方の企業にも言える。都市部の人材を「単なる労働力」「単なる手足」のように見ているとうまく行かない。
地方の企業として、将来目指したいビジョンがある。その「想い」の実現のためにがんばっている。だが、それを実現するためには、リソースや専門的な知識が必要……。
「想い」をもった都市部の人材とつながるためには、企業にも、「将来目指したいビジョン」(つまり、想い)が必要なのである。
また、行政機関や地域の人の意識もそうだ。せっかく、地域に関心を持って、足を運んでくれるにも関わらず、「移住候補者」のような扱いで、「早く移住してほしい」と急かしたり、「どうせ、いつか帰っちゃうんでしょ」のように、よそ者扱いしたりするとうまく行かない。
まずは、地域に関心を持ってくれた「想い」に感謝し、「この地域に関わってよかったな」と思っていただけるような、ファンになっていただけるような関わりが必要なのである。
急速に立ち上がってきた地方×複業の仕組み
これまで、イベントはできても、自分の周囲で「具体的な動き」にするのは、なかなか難しい……と感じてきた。
しかし、ここにきて、都市部のビジネスパーソンと地方の企業をマッチングする仕組みや、政府の取り組みが急速に立ち上がってきた。また、地方でも少しずつ動きが出てきた。こういった仕組みをうまく使えば、地方×複業は実現できそうだ。
その一例を紹介しよう。
都市部のビジネスパーソンと地方の企業をマッチングする仕組み
行政機関が地域限定で行っているものや、企業が全国規模で行っているものまでさまざまだが、都市部のビジネスパーソンと地方の企業をマッチングする仕組みが出来てきた。
政府の動き
政府の動きも活発になってきている。
「まち・ひと・しごと創生会議」では、地方創生のための「関係人口の創出・拡大」施策の一つとして、「副業・兼業として地域にかかわる人材の活用」を挙げている。
また、地方銀行や人材紹介会社などと連携し、東京圏で働く人材が、地方企業で兼業や副業するよう後押しする制度を2020年度に創設するという。
経済産業省 関東経済産業局は、複活という地方×複業推進事業をはじめている。
地方の動き
今年に入って、地元新潟で地方×複業の講演依頼が数回あった。
また、地元メディアにも取り上げられた。「新聞みたよ」「何かやっているらしいね」と声を掛けてくれる人も増えた。また、地元の行政機関も耳を傾けてくれるようになってきた。昨年はあり得なかったことである。
少しずつではあるが、認知が進んできた感じがしている。
「地方×複業」を流行で終わらせないように
この1年で、地方×複業の「潮目が変わった」とわたしは感じている。いままでにない働き方が認知され、さまざまな仕組みができつつあるのはうれしいことだ。
一方で、急速に広がるある種の「流行」に、不安を感じることがある。
前述したように、地方×複業では、「想いのマッチング」が重要だが、地方企業の業務の切り出しや、都市部ビジネスパーソンの想いやスキルのヒアリングがあいまいなまま、「条件でのマッチング」をしてしまうのが怖い。
なぜなら、想像していた仕事のイメージと、実際の内容が違うと、「地方で複業なんて、やっぱりダメじゃないか」になってしまうからだ。
また、このような「流行」が起きると、さまざまな人や企業が参入するだろう。すると、それぞれの間に競争が起こって、「我先に」といった状況になりかねない。
もちろん、競争が悪いわけではない。だが、地方はどの地域も困っている。競争や利益が優先となり、それぞれの地域が、別の地域を蹴落とすような「奪い合い」「競い合い」の感じだとおもしろくないし、美しくない。
地方の困りごとを共有しつつ、それぞれの地域の特色や違いを打ち出しながら、地方の企業と都市部のビジネスパーソンとの「想いのマッチング」が進み、いい意味での「選択」できる形だといいなと思っている。
地方×複業の成功を左右する「チームワーク」の形
人口減少、東京一極集中の問題を前に、「わたしに、何ができるだろう」と考える。
地方の企業と都市部の人材をマッチングするさまざまな「仕組み」が立ち上がりつつあるいま、新たな仕組みを乱立させるよりも、すでにあるプログラムを活用したいと思っている。
一方で、地方の企業や行政機関と、都市部の人材がつながるためには、それぞれの気持ちが分かる「パイプ役」「コーディネート役」の存在が必要なのではないかと思っている。わたしは、地方と都市部の「パイプ役」になりたい。
また、地方の企業と都市部の人材が円滑に仕事をするためには、リモートワークの環境が必須である。
わたしが地方を軸に、フルリモートで複業できているのは、離れていても仕事が円滑にできるグループウェアをはじめとしたオンラインツールや、その上でやりとりされるコミュニケーションやチームワークがあるからこそである。
言い換えると、地方×複業は、これまでにない「チームワークの形」をつくる作業でもあるのだ。遠隔で仕事をするには、相応のノウハウがある。
サイボウズの理念は「チームワークあふれる社会を創る」である。わたしはこの、距離を越えて、想いでつながった、新しい「チームワークの形」「働き方の形」を伝えていきたいと思っている。
近い将来「東京」と「地方」の境がなくなる
この記事では、人口減少、東京一極集中という課題を踏まえ、「地方」と「東京」をあえて強調してきた。
だが、インターネットがあれば、いつでもどこでも仕事ができるいまの時代、本当は、「地方だ」「東京だ」と分け隔てること自体、実は、あまり意味がないのかもしれない。
「東京でも働きながら、地元や地域の役にも立ちたい」――いままでの常識では、このような願いは叶わなかった。
だが、いまは違う。まず、都市部のビジネスパーソンと地方の企業、そして、地域を「想い」でつなぐ。そして、働く環境やツール、その上で機能するコミュニケーションやチームワークを整える。そうすれば「東京でも働きながら、地元や地域の役にも立つ」は実現できる。
そして、近い将来、わたしたちはこう言うのだ。「人口減少って“危機”だと思っていたけど、自分がやりたい仕事をしながら、地域の役にも立つ働き方ができる“機会”だったんだね」と。
執筆・竹内義晴/イラスト・マツナガエイコ