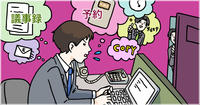サイボウズ式編集部より:9月も中旬になりました。新卒で会社に入り、部署に配属され、ようやく仕事に慣れてきた方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。そんな中で、「自分はまだ何もチームに貢献できていない」と悩みを抱えている方は多いのでは? 著名ブロガーによるチームワークや働き方に関するコラム「ブロガーズ・コラム」。今回は、新人にありがちな「無力感に対する悩み」をあらためて考えてみようと思います。 ブロガーズ・コラム チーム4人でお届けします。第3回目は桐谷ヨウさんです。
新人は「無力感」を感じがちなようです。僕自身、学生時代の根拠なき自信が消滅するくらい「俺って何もできない!」と思わされました。そう、絵に描いたような無能でした。 自分の経歴を書くと、ブロガーズ・コラムのメンツの中でも、特に大企業に所属していました。これはベンチャーと比較して「即戦力」を求められにくい環境で育ったということを意味します。 前回の日野さんのコラムで書かれたように「新人=コスト扱い」されていたのですが、数年間は「君にはまだできなくて良いよ」と、許容してもらえる環境で育ったわけです。それは人事の新人育成方針を見ても明らかでした。 誰もがそのような環境というわけではないでしょうが、そういった背景を持つ自分が書けることは「無力感を持つこと自体は仕方がない」こと。だけど、「焦る必要はない」ということです。焦ることで、近視眼的な視点が身についてしまいます。近視眼的な視点とは、先入観にとらわれた、狭い視点のこと。 振ってもらった作業をこなしただけで、仕事ができる気になってしまうのです。そうならないために大事なことを書いていきたいと思います。メンターになる先輩を自分で見つけよう。
1つめは、無力感のある新人のうちにメンターになる先輩を自分で見つける、ということです。 学生と社会人のちがいのひとつは「時間のなさ」です。とにかく社会人は時間に余裕がありません。それは週5日間は確実に拘束されてしまうという制約、そして役職が上がると自分だけでなく、他人を気にかける必要が出てくるからです。 その点、新人は(比較的)時間に余裕があります。よって自分は「最後のモラトリアム期間」として位置づけていました。意識が低かった自分が本気で仕事に取り組んだのは3年目になってからです。 この時期、自分が考えていたのは「できる人ってどんなことをしているのだろう?」でした。いろいろな人の仕事の仕方をとにかく「見る」ことに徹したのです。 自分が決めていたのは、会社で決めてもらったメンター役の先輩の意見を絶対視しないということでした。本当にかわいげがない新人だと思いますが、メンターは当たりハズレがあると考えていたからです。 実際、中堅を教育するためにメンター役に指名している背景があるのです。だからこそ、メンターの意見が「できる社会人ならば誰もが意識していること」なのか、「単にその人の価値観で大事にしていること」なのかを見極める必要があると思っていたのです。これは正解でした。 メンターの言葉に惑わされずに、いろいろな人の仕事の仕方を観察した結果、一般に「仕事ができる」と表現されるあいまいな言葉には、いくつかの要素があることが分かってきました。そしてすべての先輩=すごい人では決してないことを確信しました。(すべての先輩にはメンターも含まれます。) そう、すべての人には長所も短所もあります。できる人とは長所を最大化して、短所を最小化している人たちだったのです。仕事にはコミュニケーション能力が大事と言われますが、ないのに優秀な人だっています。それはコミュニケーション能力の不足を補って余りある、その人の見識が評価されているということなんですよね。 ここで重要なのは、「自分にフィットする長所から学べ」ということです。仕事の進行に大きく支障をきたす短所はある程度、改善する必要があります。が、もともと向いていないことを改善してもたかがしれています。それならば、自分の延長線上にある人がどのような仕事の仕方をしているかをまねた方が結果につながります。同時にその人の短所を顕在化させないテクニックを拝借すれば、それは自分にも援用できます。(長所は短所と抱き合わせなので、その人は自分と似た短所を持っていることが多いから) 最初の師匠であるメンターには逆らってはいけないと思うかもしれません。でも、先輩を査定するくらいの感覚でちょうど良いです。「あなたが本当にスゴイのであれば、私を納得させてください」と思っていればいいのです。先輩の言うことは絶対、なんてバカげた話ですから。 こういった緊張感は職場にも良い影響を及ぼします。もちろん不遜な態度を取ってはいけませんが、先輩に緊張感を与えるのはあなたにできる貢献のひとつです。本当に無能な先輩でないかぎり「なるほど」と思わせてくれる思考を披露してくれることでしょう。そのときにはその優れた部分を素直に学ぶ姿勢を持っていれば、納得を追求するのは重要なことです。